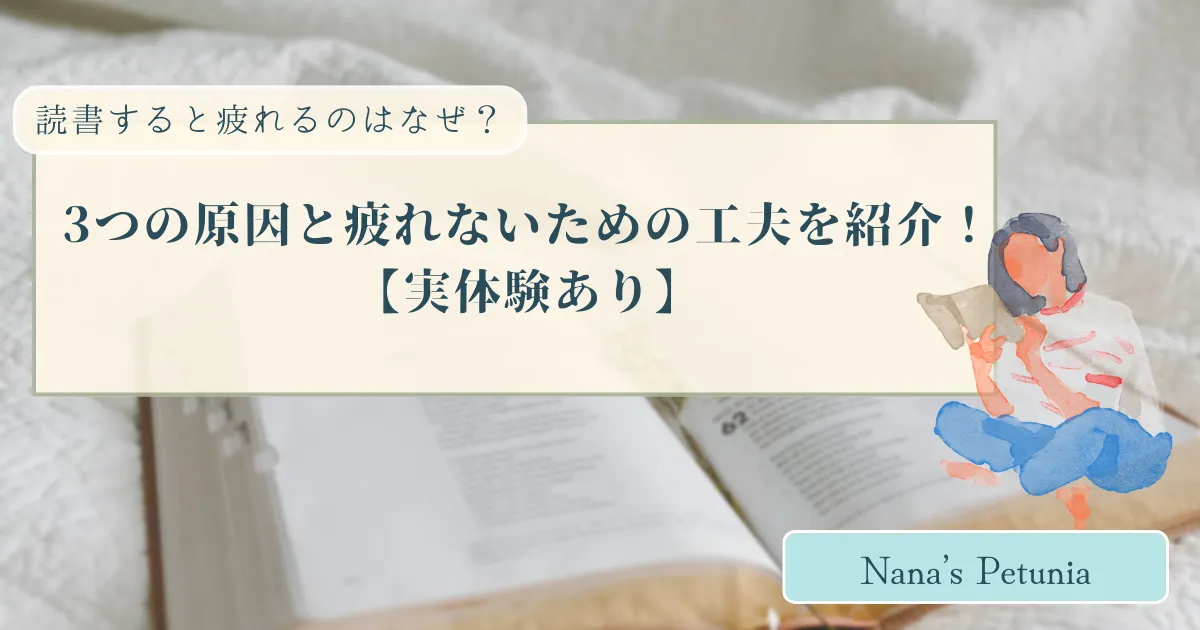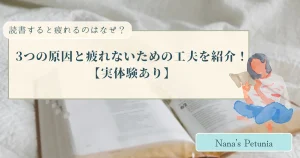読書したいのに、なぜかすぐに疲れてしまう……



ページは開いたのに、まったく頭に入ってこない……
そんな読書疲れを経験したことはありませんか?
私自身、うつ病と向き合う中で、読書がまったくできなくなる時期が何度もありました。
でも今では、年間130冊以上の本を楽しめるように。
実は、読書疲れにはいくつかのパターンがあり、それぞれに合った工夫をすれば楽に読めるようになるんです。
この記事では、身体・脳・心の状態ごとに「読書で疲れる原因」とその対策をまとめました。
さらに後半では、“読む”のがしんどいときでも楽しめる「聴く読書」のメリットについてもご紹介しています。
「読書を楽しめるようになりたい」と思っているあなたに、きっと役立つ内容になっているはずです。



ぜひ、気になるところから読み進めてみてくださいね!
あなたが読書をしていて疲れるのはどこ?



本を読んでいたら、なんだかすぐに疲れてしまう……
実はこの“読書疲れ”、原因を大きく3つに分けて考えることができます。
- 目/肩/腰などの身体
- 脳
- 心
このパートではそれぞれの疲れをもたらしている原因についてご紹介していきます。



自分の場合はどれに当てはまりそうか考えてみてくださいね。
目/肩/腰などの身体が疲れやすい原因|読書環境や姿勢
まず考えられる疲れは、「読書中に目/肩/腰などの身体に負担がかかっている」ことによるものです。
文字を追っていると目がかすんでくる
首や肩が痛くなってくる
そんな人は、読書の環境や姿勢を見直すことから始めるのがおすすめ。



座っている椅子や照明の明るさを少し変えてみるだけで、読書がグッと快適になるかもしれません。
なお、読書中の明るさは300~500ルクス程度が理想とされています。
長時間の読書の際は、もう少し暗めの200~250ルクス。
あたたかみのある電球色であれば、リラックスして読書に集中できますよ。
脳が疲れやすい原因|本が難しすぎる・一度で完璧に理解しようとしている
続いて考えられる原因は「難易度の高い本を選んでいたり、すべてを一度で理解しようとしていたりしている」ことです。



あなたが今読んでいる本は、自分にあったレベルのものでしょうか?
情報処理量が多すぎると、認知的負荷が高まり、脳がオーバーヒートしやすくなります。
特に、専門用語が多いビジネス書や哲学書などは要注意。
「ついていけないかも…」と感じたら、無理せずスパッと諦めてしまうのもアリです。
新しいジャンルに挑戦するのであれば、初心者向けと明記されているものなどから始めるのがおすすめですよ。
また、一度読んですべてを理解しようと意気込みすぎている可能性もあります。
基本的に、一度読んだだけでその本のすべてを理解するのは難しいものです。
一言一句すべてを逃さないようにしようとしてしまうと、自然と力が入ります。
わからなかったところには印をつけるなどして、「後から調べればOK!」と考えるのがおすすめです。
心が疲れやすい原因|ストレスが溜まっている・内容がハードすぎる
続いて考えられるのは、「そもそも読書するだけの体力・気力がない」可能性と「選んだ本が心にダメージを強く与える内容である」可能性です。
ストレスが溜まっている状態では、読書しようと思ってもなかなかできない場合があります。



私自身、心がやられてしまっているときは読書に集中できなくなります…。
今のあなたには、読書よりもまず休息が必要なのかもしれません。
さらに、本の内容によってはさらに心理的負担をかけてしまう場合も。
たとえば、家族の死やトラウマを扱った作品や、社会問題を鋭くえぐるノンフィクションなどは、そのタイミングでは読むべきではないかもしれません。
【原因別】読書で疲れないための対処法
先ほどご紹介した、読書で疲れる原因ごとにおすすめの対処法をご紹介していきます。



自分のタイプにあてはめながら、無理のない読書スタイルを探ってみてくださいね。
【目/肩/腰の疲れが原因なら】身体に負担のかかりにくい読書環境を用意
目や肩などに疲れを感じやすいなら、いかに身体に負担のかかりにくい読書環境を用意するかが重要。
私が個人的におすすめしたい、読書環境づくりのポイントは以下のとおりです。
読書姿勢を整える
- 深く腰掛けられる椅子を使い、背中をしっかり預ける
- 本を置けるクッションやブックスタンドで手首や首の負担を軽減
- 足が床にしっかりつく高さの椅子を選ぶ
目が疲れにくい照明にする
目に優しい読書には、300〜500ルクスの照明が理想的。
夜間や長時間の読書には少し落ち着いた電球色(暖色系)がおすすめです。
また、スマホやタブレットでの読書にはブルーライトカット機能をONにするのもお忘れなく。 眼精疲労がひどい場合は、「紙の本に戻す」という選択肢も検討してみてください。



なお、このあとご紹介する”聴く読書”なら目の負担ゼロなのでとってもおすすめですよ!
【脳の疲れが原因なら】読書のハードルを下げてリラックス
脳の疲れを感じやすい人は、読むことそのものを気負いすぎている可能性があります。
以下のような読み方を取り入れて、脳の負荷を軽くしていきましょう!
完璧主義読書をやめる
- 一言一句を理解しようとせず、「ざっくり読む」くらいでOK
- わからない言葉は飛ばして読んで、後から調べるくらいがちょうどいい
- 読み飛ばし・途中でやめるのも“あり”だと自分に許可を出す
難易度を下げる or 読み慣れたジャンルに戻る
- 難解な専門書ではなく、自己啓発本・エッセイ・エンタメ小説などから始める
- 以前に読んで「楽しかった」と思える1冊を再読するのもおすすめ
【心の疲れが原因なら】まずは休息第一!本の選び方に気をつける



どうしても読書に集中できない…



“今は読まない”という選択も、大切だと思います。
「少しなら読めそう!」と感じられたら、感情を揺さぶる系の小説や社会派のノンフィクションなどは避け、イラストの入ったエッセイ本や児童小説から手に取ってみるのがおすすめです。



心が疲れたときにおすすめな本はこちらの記事でまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
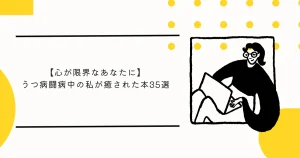
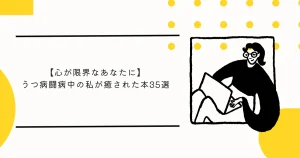
心の疲れをケアしたいと感じた方に…
読書の話題とは離れてしまうのですが、私がとってもお世話になっているメンタルケアアプリがあるので、よければこちらの記事も参考にしてみてくださいね。


読書で疲れやすい人が陥りがちな勘違い5選
「読書すると疲れる…」と感じる人の多くは、無意識に“読書に対する思い込み”を抱えていることがあります。
ここでは代表的な5つの勘違いをご紹介。



意識を少し変えるだけでグッと楽に読めるようになるかもしれません。
勘違い1:一言一句すべて理解しなくてはいけない
本を読むときに「全部理解しなければ!」と力んでしまうと、脳が疲れやすくなります。



特に専門書や難しい内容の本は、一度で理解できないのが普通です!
わからない部分は飛ばして、後で調べてみるくらいでOK。
“ざっくり読む”くらいのスタンスで読書を楽しみましょう!
勘違い2:読み始めた本は完読しなくてはいけない
「せっかく買ったのだから最後まで読まないといけない」
──この考え方をしてしまうと、読書が苦行になりがちです。
面白くないと感じたら、途中でやめてしまってもOK。



「気が向いたら、いつか読み直そう」くらいの気持ちでいましょう〜!
勘違い3:役立つ本しか読むべきではない
「せっかく読書するなら、ビジネス書や実用書を読んで実生活に役立てなくては!」と思っていませんか?
小説やエッセイ、漫画のような「役に立つかはわからないけど楽しい本」も、立派な読書です。



個人的には、「役に立てよう」という意識を捨てて読書したほうがむしろ得るものが多いような気もします!
勘違い4:本が読めないのは気合いが足りないせいだ
「集中力がない自分が悪い」と考えてしまうのもありがちな勘違い。
実際には、環境やストレスといった要因で読めないことも多いです。



無理に気合いで読もうとすると、余計に読書が苦行になり疲れやすくなるので注意しましょう。
勘違い5:読書のためにはまとまった時間を用意すべきだ
「1時間以上は読まないと」などと思う人も多いですが、そんなことはありません。
5分でも10分でも、本を読めば立派な読書。



通勤中の数ページ、寝る前の10分など、スキマ時間を積み重ねる読書のほうが習慣化もしやすく、疲れにくいですよ。
すべての読書疲れに!”聴く読書”なら圧倒的に疲れにくい
ここまで、読書が疲れると感じてしまう原因を3つご紹介してきましたが、そのすべてに対処できるのが「聴く読書」。



圧倒的に疲れにくく、日常に読書を取り入れやすくなるので、私が個人的にもっともおすすめしたい対処法です。
\ 30日間の無料体験アリ /
読書疲れの人に”聴く読書”をおすすめしたい3つの理由
- 目の負担ゼロ!
- ながら読書可能だから日常生活に取り入れやすい!
- 寝る前の”聴く読書”をルーティン化すれば睡眠導入代わりに!
1. 目の負担ゼロ!
本やスマホの文字を長時間追っていると、どうしても目が疲れてしまいますよね。
特にパソコンやスマホを日常的に使っている人は、眼精疲労や肩こりが読書疲れの原因になることも多いです。
2. “ながら読書”可能だから日常生活に取り入れやすい!
従来の読書は「机に座って本を開く」など、ある程度まとまった時間と集中力が必要でした。
でも“聴く読書”なら、通勤・家事・運動中など「ながら」で楽しめるんです。



「読書は疲れる」という人も、“ながら読書”であればリラックスして本を楽しめると思います!
3. 寝る前の“聴く読書”が睡眠導入代わりに!
夜に紙やスマホで読書すると、ブルーライトや集中しすぎで逆に目が冴えてしまうことがあります。
その点、やさしい声で語られるオーディオブックをBGMのように聴くと、自然とリラックスモードに入りやすいんです。
実際に、寝る前に“聴く読書”を取り入れると…
- 余計な考え事が減って気持ちが落ち着く
- ナレーターの声に集中しているうちに心地よく眠れる
- 読書と睡眠を結びつけることで、毎晩の習慣になりやすい



「文字を読むのはつらいけど、寝る前に物語を楽しみたい」という人にピッタリです。
こちらの記事ではAudible(オーディブル)を使った寝落ち読書について解説しているので、合わせてチェックしてみてくださいね!
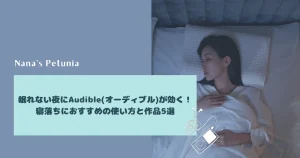
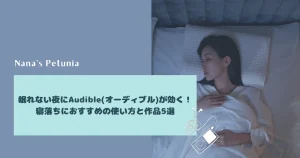
【実体験】うつ病の私も”聴く読書”で本が無理なく楽しめるように!
私自身、うつ病で本を開くのさえしんどい時期がありました。
読もうとしても、文字の上を目が滑るような感覚でまったく頭に入らない…。
そんなときに出会ったのが「聴く読書」でした。
最初は半信半疑でしたが、目を使わなくてもストーリーが楽しめるのは助かりました。
特に私の場合は、
- 寝る前にベッドでAudible(オーディブル)を流すことで、ネガティブな思考から気を紛らわして物語に逃げ込める
- “本を読めた”という小さな成功体験が自己肯定感につながる
といった効果がありました。
「読書したいけど疲れる」という人にとって、聴く読書は“回復の入り口”になると思っています。
詳しいAudible(オーディブル)のレビューは以下の記事にまとめているので、ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。
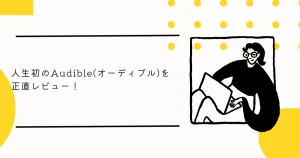
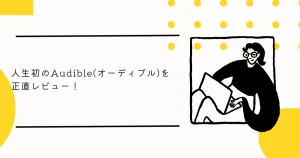
【注意点】こんな人は”聴く読書”に向かない可能性も
もちろん、Audible(オーディブル)がすべての人に向いているわけではありません。
たとえば
- 耳からの情報処理が苦手な人 → どうしても頭に入らないと感じる方は、紙や電子書籍のほうが合うかもしれません。
- 紙の本の質感が好きな人 → 本を手に取り、紙をめくる体験そのものが読書の醍醐味だと感じる方には物足りなさがあるかも。



Audible(オーディブル)なら30日間の無料体験期間があるので、まずは自分に合うかどうか確かめてみてくださいね。
\ 30日間の無料体験アリ /
Q&A
このセクションでは、読書で疲れやすいと感じる人のよくある質問に回答していきます!
Q1. 読書するとすぐ眠くなるのはなぜ?
A. 読書で眠くなるのは「リラックス効果」が出ているサインでもあります。
ただし照明が暗すぎる、内容が難しすぎる場合は眠気を誘いやすいので、環境を整えてみてはいかがでしょうか。
Q2. 読書で頭痛がするときの対処法は?
A. 照明不足や眼精疲労が原因かもしれません。
ブルーライトカット眼鏡を使ったり、紙の本に切り替えると改善することがあります。
目を使わない「聴く読書」なら、比較的ラクに本を楽しめますよ。
Q3. 読書に集中できないのはなぜ?
A. 本が難しすぎる、脳が疲れている、心がストレスを抱えているなど原因はさまざまです。
「簡単な本を選ぶ」「短時間だけ読む」といった工夫をしてみるのもおすすめですよ。
Q4. 読書が苦手でも楽しめる方法はある?
A. もちろんあります!
漫画や図解本、短編集から始めるのも良いですし、Audible(オーディブル)などの聴く読書なら活字が苦手でも物語を楽しめます。
Q5. Audible(オーディブル)の料金プランは?
月額1,500円(税込)で、対象の12万冊以上が聴き放題です。
30日間の無料体験もあるので、まずは気軽に試してみるのがおすすめです。
Q6. 聴く読書って頭に入らないのでは?
私自身、最初のころは不慣れで巻き戻すことがありました。
無理に頭に入れようとせずにまずは「BGM感覚」で聴いていくことで、耳が慣れて自然と頭に入ってくるようになりますよ!
Q7. Audible(オーディブル)は合わないと思ったら解約できる?
もちろんです。
簡単な手続きでいつでも解約可能で、違約金がかかることもありません。
なお、解約後もアカウントを削除しなければ、いつでも再開することができますよ。
Q8. Audible(オーディブル)にはどんなラインナップがあるの?
Audible(オーディブル)のラインナップは、小説/実用書/エッセイ、さらにはポッドキャストまでさまざま。
おすすめの小説については以下の記事でご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね!
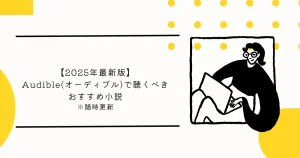
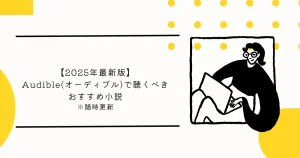
\ 30日間の無料体験アリ /
【まとめ】”聴く読書”を取り入れて、無理のない読書習慣を始めよう!
「読書すると疲れる…」と感じるのは、よくある現象です。
目や肩などの身体的な疲れ、脳のオーバーヒート、心のコンディション。
原因を知って工夫すれば、もっと楽に読書を楽しめます。
読書で疲れやすいときの個人的なおすすめは「聴く読書」。
私自身、うつ病で本が読めなくなった時期に「Audible(オーディブル)」が救いになりました。



本来、読書は気楽に楽しむものだと思います。
疲れにくい方法を取り入れながら、あなたのペースで本を楽しんでくださいね。
\ 30日間の無料体験アリ /